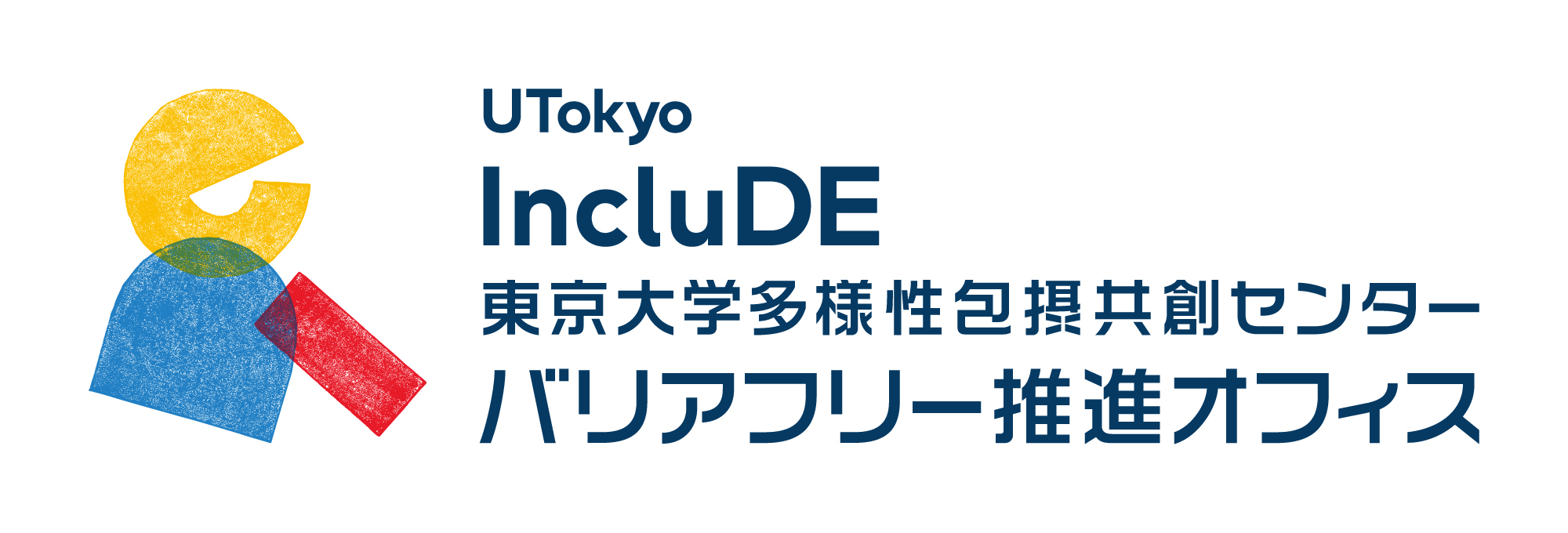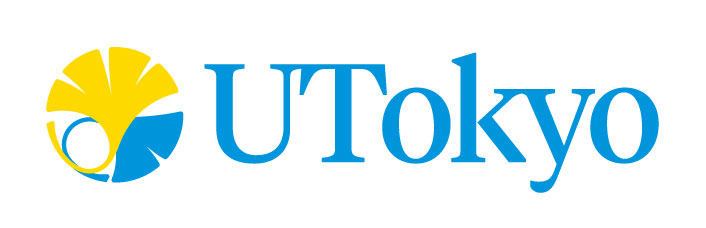オフィス長挨拶
オフィス長 松田 雄二

2006年、国連で「障害者権利条約」が採択されました。これは、障害者の人権の確保や権利の実現のための措置等について定めたものですが、この条約の中心的な考え方に、「障害の社会モデル」があります。「障害の社会モデル」とは、障害のある人々が経験する様々な困難は、社会がそれらの人々にとって使いにくくできているためであり、そのような困難を解消する責任は社会の側にある、とする考え方です。この考え方は、2013年に日本で制定された障害者差別解消法などにも取り入れられ、現在では環境整備を行う上での基本的な考え方となっています。
この障害の社会モデルの立場に立って、社会に存在する様々な障壁を解消することが望まれますが、特に建築環境など物理的な障壁について、その解消が現実的には容易ではない場合が多々存在します。そのような場合、障害者権利条約や障害者差別解消法では「合理的配慮(reasonable accommodation)」を行うことが求められています。この合理的配慮とは、環境を整備する側が、障害者が他のものとの平等を基礎として、人権及び基本的自由を確保するための必要かつ適当な変更および調整で、過度の負担を課さないものとされています。
東京大学も、ここでいう社会に他なりません。東京大学憲章には、本学で学ぶ学生、本学で働く職員、本学で研究と教育にあたる教員からなる全構成員が、障害等を理由に不当な差別を受けることなく、その個性と能力を十全に発揮しうる公正な教育・研究・労働環境の整備を図ると宣言しています。バリアフリー推進オフィスは、その憲章の精神に則った大学キャンパスを実現すべく、本郷キャンパスと駒場 I キャンパスに支所を置いて障害のある学生、教職員のバリアフリー支援のための活動を進めています。
本学では、障害のある学生や教職員を支援するにあたり、部局は人的・物的サポートを、本部は財政的措置を、そしてバリアフリー推進オフィスは支援ノウハウの提供を担っています。そのため、バリアフリー推進オフィスでは支援の経験を積んだスタッフが、障害のある学生・教職員と部局の間に立ち、建設的対話と合理的配慮の実現をサポートしています。また、学生サポートスタッフの要請やアクセシビリティマップの作成と更新、各種情報発信なども行っています。今後、大学を誰にでも開かれた場であり、かつ様々な視点での多様性が実現された環境とするために、より一層の活動の充実が求められると考えております。全学の皆様のご理解とご支援を、心よりお願い致します。